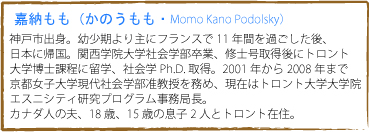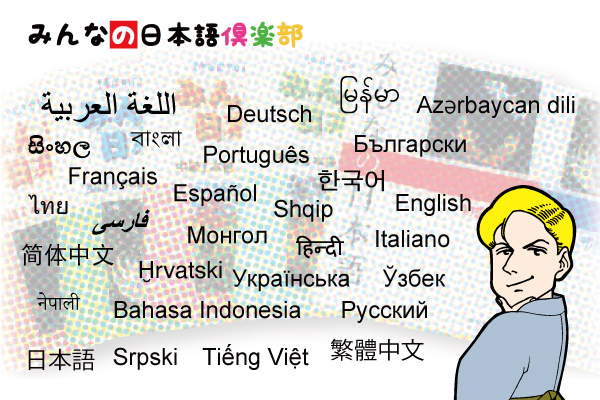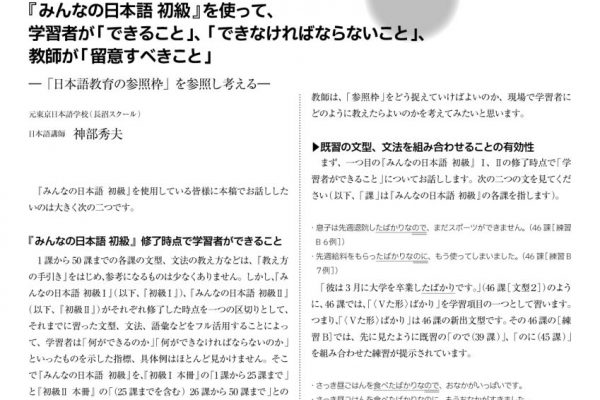『サードカルチャーキッズ』
の翻訳者のお二人が、サードカルチャーキッズの母親としての日常的な視点と、
研究者としてのアカデミズムの観点、の2つの立場から
「サードカルチャーキッズの今!」をお届けします!
**************************************
| 嘉納もも |
こんにちは。
前回のブログ記事を担当した日部八重子さんと『サードカルチャーキッズ』を共訳した嘉納ももです。
国際移動の真っ只中にいる日部さんは「当事者」としての臨場感あふれるレポートをお届けしていますが、私はちょっと違った「研究者」の立場からの記事を書いていこうと思います。
私が「サードカルチャーキッズ」(以下TCK)という言葉を自分の授業や研究の中で使い始めたのは2003 年のことでした。
TCKと同じように、親の仕事の関係で海外渡航し、戻ってくる子どもたちのことを日本では「帰国子女」と呼びます。
ではちゃんと「帰国子女」という呼び名があるのに、なぜ「TCK」を改めて用いる必要があるのでしょうか。
この二つを比べた場合どんな違いがあるのか、について私が感じていることを今日はお話しさせてください。
「帰国子女」と聞くと、皆さんはどのような人たちを思い浮かべるでしょうか。
大学で「帰国子女論」という講義を担当していた時、私はいつも最初の授業で学生にアンケートを取るようにしていました。
200人以上の受講者の回答をまとめると、大多数が「小学校低学年から中学校まで、欧米諸国に長期間滞在し、外国語(特に英語)が堪能で、帰国時には日本語が少し不自由」という帰国子女に対する「イメージ」を共有していることが判明しました。
面白いことに毎年、ほとんど同じような結果が出てくるのです。
このようなイメージがいつから、どのように形成されて来たのか、についてはまた別の機会にお話しするとして、とりあえず日本人の間では帰国子女の存在が広く知られているという点と、「ステレオタイプ」ともいえるほどの非常に偏ったイメージが共有されている、という点が学生アンケートから伝わってくるのではないでしょうか。
一方TCKは、著者のポロックとヴァン・リーケンによると、本国(アメリカ)でその存在が最近までほとんど注目されることはなかったようです。
他にも外国からやってきた人たち(たとえば移民や留学生など)が大勢いることからその中に埋もれてTCKは目立たないのだ、と著者たちは指摘しています。
周囲の人と言葉が通じないわけでもない、外見的に特に変わっているわけでもない。
それなのになぜ違和感を覚えるのだろう、とTCKの多くが疑問を持ちます。
理由が分からないために孤立したり、体験を封印したりしてしまいます。
その違和感が、小さい頃から国際移動を経験し、厳密にはどこの国の文化でもない「サードカルチャー」の中で育ったことから来るのだ、と教えられた時、TCKたちが大きな安堵を覚えるのはそのためでしょう。
こうしてみると、「TCK」という名前が解放感を与えるのに対して、「帰国子女」というレッテルは非常に限定的な、束縛の強いものだと私は思います。
それは学生アンケートにも見られるとおり、帰国子女には何らかの「外国生活によってもたらされた成果」みたいなものが期待されているからではないでしょうか。
もっと平たく言えば、「外国語(特に英語)ができること」、「外国(これも要は欧米諸国)の文化や外国人の思考パターンに馴染みが深いこと」などが帰国子女には当然、求められるということです。
実際にこのような期待に応えられる場合はよいでしょうが、たいていの人には相当なプレッシャーになります。
ある年、お父さんの駐在に伴ってマレーシアに何年か滞在したという学生が私のゼミに入ってきました。
彼女は「ずっと自分のことを帰国子女じゃないと思っていた」と言いました。
なぜなら海外に住んでいたといっても、クアラルンプールの日本人学校に通っていたし、現地の人と親しく交流した経験もなく、英語がそう得意でもないので、「いわゆる」帰国子女のイメージに当てはまらないから、というのが彼女の説明でした。
TCKという呼び名に出会い、その学生は生き生きとして自分の体験を元にした研究を完成させました。
日本人学校の同窓生にインタビューを行った結果、従来の帰国子女研究からはなかなか浮かび上がってこなかった体験談が収集できたのです。
ほんの一部の人の体験しか反映していない「帰国子女」のステレオタイプを見直すことももちろん大事ですが、新たに「TCK」という概念を用いて国際移動する子どもたちの体験を解釈するのもよいかと思います。
次回は著者のポロックとヴァン・リーケンたちが「TCKの親として気をつけなければいけないこと」として挙げている点についてお話ししたいと思います。