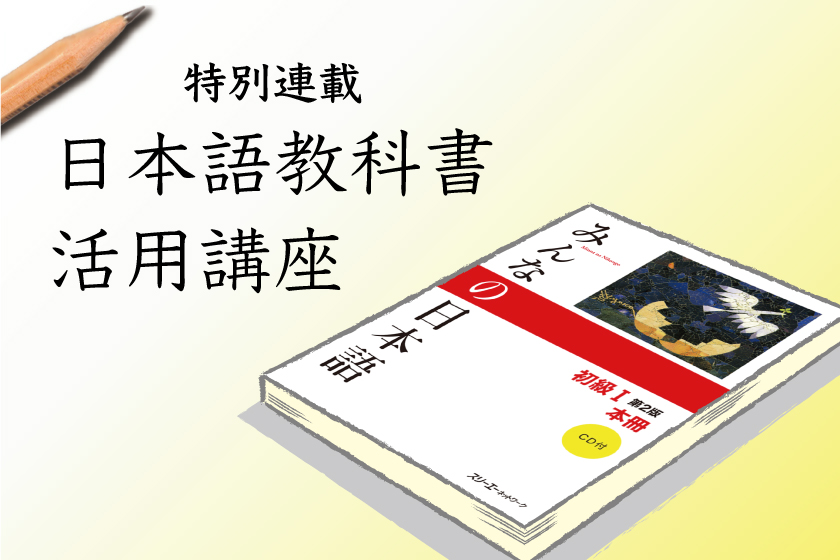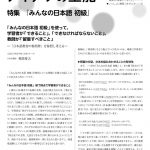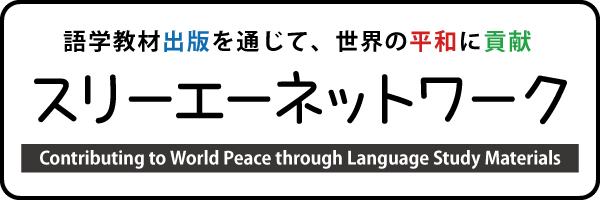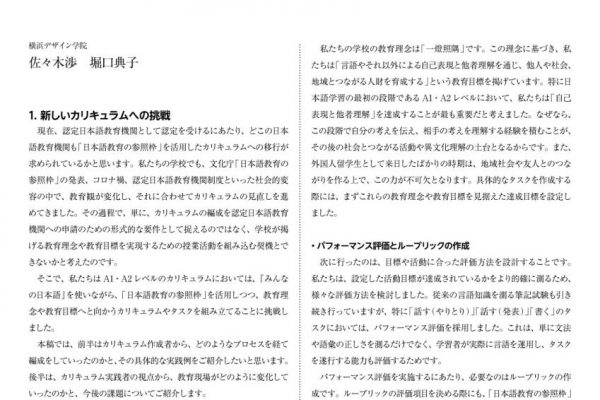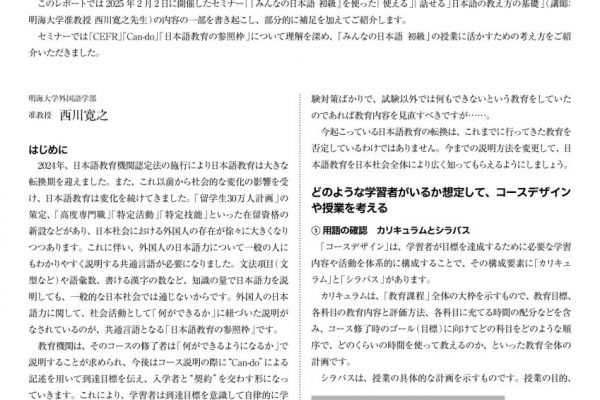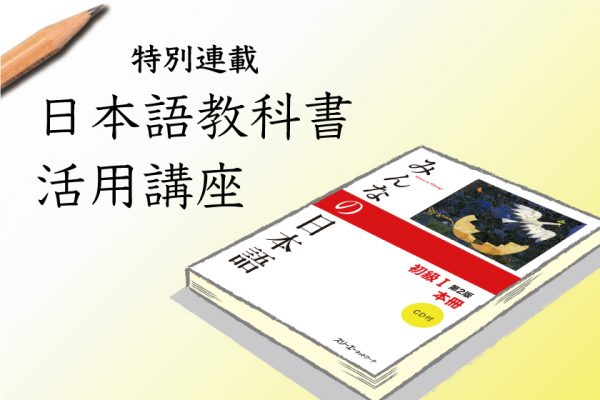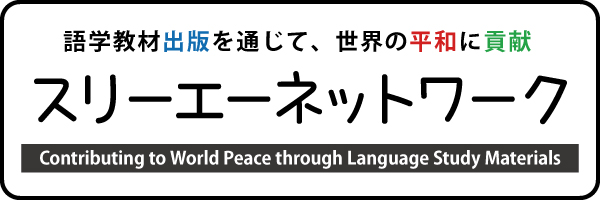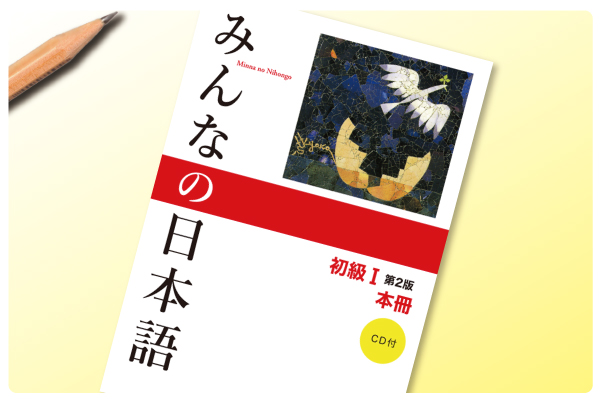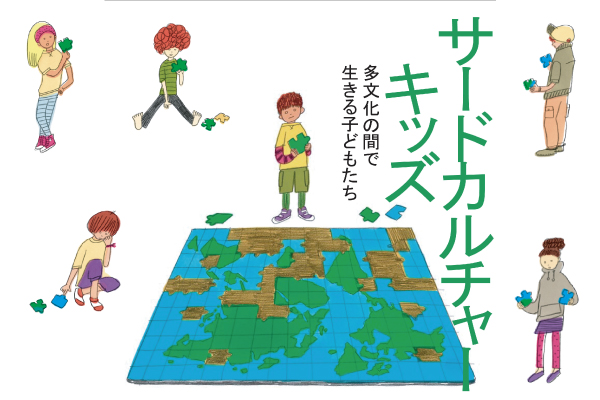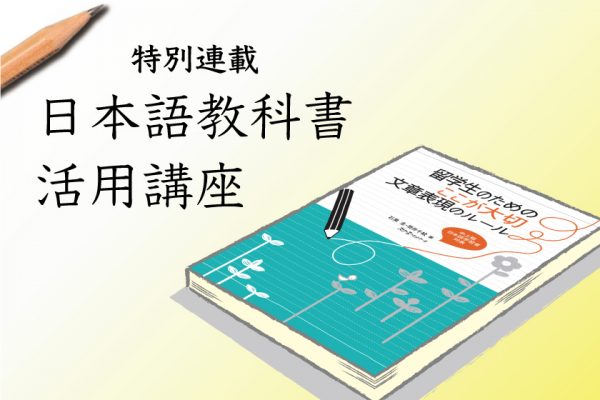佐々木渉 堀口典子
*ご所属・お肩書などは2025年10月現在のものです
1. 新しいカリキュラムへの挑戦
現在、認定日本語教育機関として認定を受けるにあたり、どこの日本語教育機関も「日本語教育の参照枠」を活用したカリキュラムへの移行が求められているかと思います。私たちの学校でも、文化庁「日本語教育の参照枠」の発表、コロナ禍、認定日本語教育機関制度といった社会的変容の中で、教育観が変化し、それに合わせてカリキュラムの見直しを進めてきました。その過程で、単に、カリキュラムの編成を認定日本語教育機関への申請のための形式的な要件として捉えるのではなく、学校が掲げる教育理念や教育目標を実現するための授業活動を組み込む契機とできないかと考えたのです。
そこで、私たちはA1・A2レベルのカリキュラムにおいては、『みんなの日本語』を使いながら、「日本語教育の参照枠」を活用しつつ、教育理念や教育目標へと向かうカリキュラムやタスクを組み立てることに挑戦しました。
本稿では、前半はカリキュラム作成者から、どのようなプロセスを経て編成をしていったのかと、その具体的な実践例をご紹介したいと思います。後半は、カリキュラム実践者の視点から、教育現場がどのように変化していったのかと、今後の課題についてご紹介します。
2. カリキュラム編成の流れ
・活動の目標設定
カリキュラムを編成するにあたり、私たちは「バックワードデザイン」という考え方に基づいて検討していきました。バックワードデザインとは、①学習目標、②評価方法、③授業内容・方法の順にカリキュラム全体を設計するという考え方です。
まず、学習目標をどのように設定したかをご紹介します。目標設定には、日本語教育振興協会「日本語教育スタンダード」、「日本語教育の参照枠」や、最新の情報となる「CEFR-CV」を読み込み、参照することにしました。ただ、それだけではオリジナリティのないカリキュラムになってしまいます。そこで、学校の教育理念や教育目標も重視しました。
私たちの学校の教育理念は「一燈照隅」です。この理念に基づき、私たちは「言語やそれ以外による自己表現と他者理解を通じ、他人や社会、地域とつながる人財を育成する」という教育目標を掲げています。特に日本語学習の最初の段階であるA1・A2レベルにおいて、私たちは「自己表現と他者理解」を達成することが最も重要だと考えました。なぜなら、この段階で自分の考えを伝え、相手の考えを理解する経験を積むことが、その後の社会とつながる活動や異文化理解の土台となるからです。また、外国人留学生として来日したばかりの時期は、地域社会や友人とのつながりを作る上で、この力が不可欠となります。具体的なタスクを作成する際には、まずこれらの教育理念や教育目標を見据えた達成目標を設定しました。
・パフォーマンス評価とルーブリックの作成
次に行ったのは、目標や活動に合った評価方法を設計することです。私たちは、設定した活動目標が達成されているかをより的確に測るため、様々な評価方法を検討しました。従来の言語知識を測る筆記試験も引き続き行っていますが、特に「話す(やりとり)」「話す(発表)」「書く」のタスクにおいては、パフォーマンス評価を採用しました。これは、単に文法や語彙の正しさを測るだけでなく、学習者が実際に言語を運用し、タスクを遂行する能力も評価するためです。
パフォーマンス評価を実施するにあたり、必要なのはルーブリックの作成です。ルーブリックの評価項目を決める際にも、「日本語教育の参照枠」や「CEFR-CV」を参照するだけでなく、教育理念や教育目標が達成されているかを測る項目を設けました。加えて、これまでの教師としての経験を活かして、評価基準を定めました。ルーブリックを作ることにより、評価の観点が明確になり、教師間の評価のずれを最小限に抑えられるだけでなく、タスクを通してどこへ向かっていくのかを教師にも学習者にも共有することができるようになりました。
例えば、「将来の夢や目標について話す」という話す(発表)のタスクでは、 次頁の図のようなルーブリックを作成しました。 このルーブリックでは、「言語方略(計画)」や「言語能力(言語運用能力)」など、複数の観点から学習者のパフォーマンスを評価します。そして、「タスクの達成度」の中に「発表」と「質疑応答」という項目を設定することで、「自己表現」の面だけでなく、「他者理解」の面の能力も測れるようにしました。

・タスク作成のプロセス
最後に、具体的なタスク作成のプロセスをご説明します。タスク作成の際、「日本語教育の参照枠」や「CEFR-CV」の能力記述文に加え、「生活Can-do」や「JF Can-do」のリストも参照しました。これらの記述文とリストを参考に、学習目標の達成に必要な能力を測るため、最適なタスクを選定していきました(下段、図2)。
そして、タスクを『みんなの日本語初級』のシラバスと照らし合わせ、どの課を学習した後に実施するのが最も効果的かを検討しました。例えば、先にご紹介した「将来の夢や目標について話す」という話す(発表)のタスクは、「~ようと思っています」「~つもりです」といった意志や予定を表現する文型を含む31課を学んだ後に行うのが最適だと判断しました。タスクの選定と配置が決まってから、共有して使用できる授業案や、スライドやワークシートなどの教材作成に取り掛かりました。目標や評価方法が決まった後に実際の授業を考えることで、「この部分、どうしようかな」と迷ったときも方針がぶれることなく、作業を進めることができました。
3. タスク例の紹介
『みんなの日本語 初級』(全50課)を学ぶ間に、「やりとり」のタスクを20、「発表」のタスクを10、「書く」タスクを10設けました。ここでは具体例として、先にも挙げた「将来の夢や目標について話す」という話す(発表)のタスクをどのように授業展開しているか、ご紹介します。このタスクは、地域や社会の人々と関わる場面を想定し、「あなたは将来どんなことがしたい?」といった話題になったときに、学習者が語れるようになることを目指しました。このタスクの活動目標は以下の通りです。
この目標を達成するため、タスクは『みんなの日本語初級』31課で学習する「~ようと思っています」「~つもりです」などの文型も駆使しながら、自分の夢や目標、そのためにこれから何をしたいかを具体的に話すように設計しました。タスクの具体的な流れは以下の通りです。
このタスクを実践するにあたり、学習者のレベルを考慮し、評価の観点はルーブリックで提示するのではなく、以下のような5つのポイントとして提示しました。
授業をする上で留意した点は、発表の前にグループ内で練習する時間を十分に設けることです。発表は学習者にとって、非常に緊張するものです。事前に練習する時間を授業内で設けることで、自分の夢や目標を語るという「自己表現」を達成できる授業デザインとしました。また、それだけでなく、他の学生の発表に対する質問を考えることで、「他者理解」という目標も同時に達成できるように心がけました。そのおかげか、1人の発表に対して、平均して4~5の質問が出てきました。質疑応答が盛り上がることは、クラスの雰囲気作りにもよい影響を与えると感じられました。


4. 協働的なカリキュラムの改善
ここまで、バックワードデザインという考え方を基盤に、「日本語教育の参照枠」などを参照しながら教育理念や教育目標へと向かうカリキュラムの編成とタスク設計のプロセス、具体例についてご紹介しました。
カリキュラム設計で目指したのは、学習者が日本語を通して自己表現をし、他者理解をすることで、社会とつながる力を育むことです。現在編成しているカリキュラムと設定したタスクは、そのための手段として、学習者たちの言語能力以外の課題遂行能力も引き出し、結果として活発なコミュニケーションを生み出すことができたと思っています。
現在は、このカリキュラムの継続的な点検と改善の段階にあります。この取り組みの一環として、カリキュラムを実施した教師へのインタビュー、およびカリキュラムを経験した学習者へのアンケート・インタビュー調査を実施しています。さまざまな人から声を聞くことで、設計段階では気が付かなかった点を知ることができたり、不安を解消したり、新たな課題が見えてきたりしています。
また、カリキュラムの編成や改善は、設計者が1 人だけで進めるのではなく、複数の現場の教師で協働する必要があります。次章からは、カリキュラムを実践している教師の視点から、カリキュラムがどのように見えているかをご紹介します。
5. 現場で運用して見えてきたこと
実践者としての視点から本カリキュラムを通して気付いたことがいくつかありました。まず、産出面においてA1・A2レベルのそれぞれで「できる」ことが明確であることが、カリキュラムを運用するうえで大きな助けになっていることです。言語活動(タスク)が設定されているため、学生が次の活動を達成するためにはどんな言語能力や言語方略が必要かを考えるようになりました。そうすると、授業は、言語能力の基礎である語彙や文法的な正確さだけではなく、「どうしてこの文型を使うのか(気持ち)」や「この文はどんな場面で使えるのか(適切さ)」という点に着目し、学生と確認する場になりました。
また、チームティーチングを行っていくうえでもプラスの効果を感じています。日々の学びの成果物として、学生の発表ややりとりは録画したり、作文はデータにしたりして記録に残しています。そして、チームティーチングの先生方にもチャットアプリで記録を見てもらえるようにしています。学生がどのような言語活動ができるようになったのか、できないのか、教師間で情報を共有できるので「次の課は、この部分を手厚く練習します。」というような提案をいただくこともあります。それぞれの先生が、次の授業をどのようにアプローチするのか、ということを考える際のヒントとして役立ててくれていることも示唆されています。学生の学びを育て、できることを伸ばしていこう、という一体感を持ってチームティーチングができていることを実感しています。
さらに、筆者自身、教師としての意識にも大きな変化がありました。それは、正しい答えを導き出す語彙や文法の試験とは違う視点で学生を観察することができるようになったことです。活動に取り組む中で、学生同士のやりとりや学生1人1人の独創性を見たり、聞いたりする機会を得られたからです。例えば、発表など人前で話すのが苦手な学生が、「しゃ」の発音に苦戦している学生に「し」と「や」を別々に発音して、それを速く言うという練習方法を根気強く教えていたことがありました。また、発表のあとの質疑応答の際、ある学生が、「質問じゃないんですが……」と前置きした後「〇〇さん、発表がすごく上手になっている。私もそうなりたい。本当にすごい。」とクラスメートの発表を褒めました。友達の発表に「憧れる」学生にとって、目標とすべき日本語使用者は、母語話者だけでなく、クラスメートにもなり得るのだ、と教えられました。こうした学生の姿から、課題を達成するために学生同士が助け合ったり、お互いの良さを見つけ合ったりできる、意味のある活動が行えていると確信できました。
もしかすると「教科書以外にも言語活動を実施するなんて、時間がない」と思われる先生もいらっしゃるかもしれません。しかし、なぜ、学生が日本で、ことばや文法を勉強するのかというと、日本語を使って進学したり、就職したりするという達成すべき目標があるからではないでしょうか。本カリキュラムでの学びを俯瞰すると、『みんなの日本語』は社会とつながるタスクを達成するために基本的なことばや文法を学ぶテキストという位置づけになりました。
また、本カリキュラムは、クラスによって実施する活動を調整して運用しています。そのため作文などは授業内で原稿用紙の書き方のルールや文章の構成の説明だけ行って、実際に書くのは週末の宿題にすることもあります。逆に授業内で準備や練習の時間を作って文法の復習をすることもあります。それでも、回数を重ねていくとそれぞれの活動の進め方がわかってくるので、授業で準備や練習する時間を設けなくても、課題を提出したり、発表したりする日までに学生たちが自律学習するようになりました。課題や発表などは、たとえ、うまくできないときがあったとしても、何回かチャンスがあるので、学生は次に向けて自分なりに修正したり、改善したりできるようになります。それぞれの活動の成果物はポートフォリオになり、学生が自ら何度も見直すことができる資料になります。またこれらは、学生1人1人が成長する過程を教師が客観的に評価するための記録になるという利点も挙げておきたいです。
最後にこれまでの反省と今後の課題についてです。この新しいカリキュラムに挑戦して感じたのは、それぞれの活動を楽しむことが大切だということです。筆者は正しく日本語が使えるかどうか、ということを追求しすぎて、「正しい」か「それ以外」という物差しでしか学生の課題を見ることができませんでした。しかし、活動を通して学生は1人1人伝えたいことがあって、それについて学生と対話しながら、日本語で伝えるための手助けをすることが教師としての役割だと考えるようになりました。そのためには、学生が「日本語でこれを伝えたい!」と思える活動を組み立てることが大切です。現在、学生に提示するタスクの種類は1つですが、複数のタスクを設定し、選べるようにすることが喫緊の目標です。学生自身が興味があるタスクを選びとることで、自主的に活動に取り組む動機につながることが期待できるからです。また、学生がこれから出ていく社会とつながるためには、複数の技能を使用できるタスクも必要です。そこで、実施した新たな試みも少しご紹介します。
6. 複数の技能を含むタスクの試み
7月の学校行事は社会見学でした。筆者が担任のA2レベルのクラスでは、横浜市で行われた「KANAFAN まつり」というイベントを訪ねて行うタスクを設定することにしました。その催しでは、留学生を対象にした合同会社説明会が行われることに着目し、学生に将来、日本で働くことを自分事として捉えて、自分が今できることと、これからできるようにならなければならないことを具体的にイメージしてほしいと考えたからです。
事前活動は、当日、自分たちが使用するワークシートの作成です。3、4人のグループで、イベントのウェブサイトから出展企業は何をする会社なのか調べ、興味を持った会社を決めること。その会社の説明会に参加して、会社の人に質問したいことを考えました。
社会見学当日は、それぞれのグループが、ワークシートをもとに会社のブースに行き、会社の説明を受けたり、質問をしたりしました。社会見学後のアンケートの回答から、「会社の人に質問したか」という問いには、19人中17人が「はい」と答えました。あらかじめワークシートで質問を考えておいたことで、積極的に会社の担当者に話を聞くことができたということがわかりました。そして、あとから会社についてまとめるため、聞いたことをメモにとったり、写真を撮らせてもらったりして情報収集もグループで協力して行っている姿が見られました。
事後活動は、グループで紹介したい会社を1つ決めて、A3サイズの紙に情報をまとめました。そして、学生ラウンジに展示するために、1つのボードに貼るというものです。多くの人に見てもらうためには、日本語の表記や文法の正確さはもちろん、「見せ方」も重要になるため、それぞれのグループで工夫が凝らされた作品になりました。
ふりかえると、学生たちはタスクを達成するために、複数の技能を使用したことがわかりました。事前活動では、ウェブサイトから情報収集するために、日本語を読む技能、社会見学当日は、説明会で日本語を聞いたり、話したり(やりとり)する技能、事後活動では、日本語を書く技能を生かすことができました。さらに、その後、学生と個人面談を行った際、将来何がしたいのか具体的に話してくれたことから、授業での活動が学生1人1人の自分事となり、実用的な活動につながったのではないかと手ごたえを感じました。
今後も、学生のニーズや各レベルを担当する教師のアイデアを取り入れ、楽しみながら日本語の複数の技能を使用できる活動をデザインし、学生と教師も新しいことに挑戦し続けたいと思います。
学校法人石川学園横浜デザイン学院日本語研究科科長。「日本語教育の参照枠」を活用したカリキュラム開発に関心を持つ。現在は、専門課程の日本語教育に携わる傍ら、同校のA1・A2レベルのカリキュラム編成及び改善などの業務に従事している。
堀口典子(Horiguchi, Noriko)
学校法人石川学園横浜デザイン学院日本語学科教員。アイスランド大学、上海海事大学で日本語講師として勤務。帰国後、企業内で外国人介護職員を対象とする日本語教材の開発や研修に従事し、現在に至る。