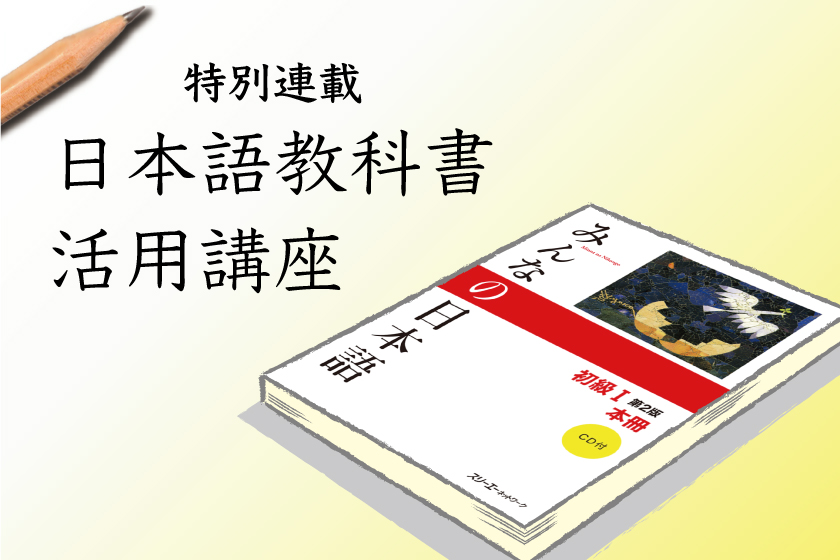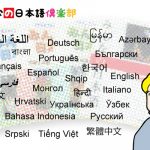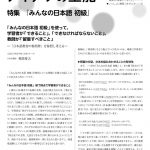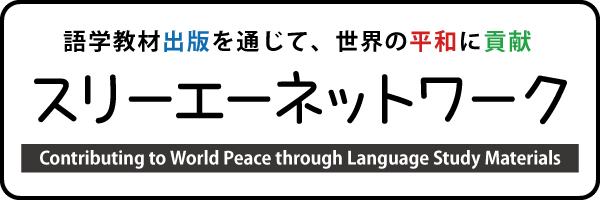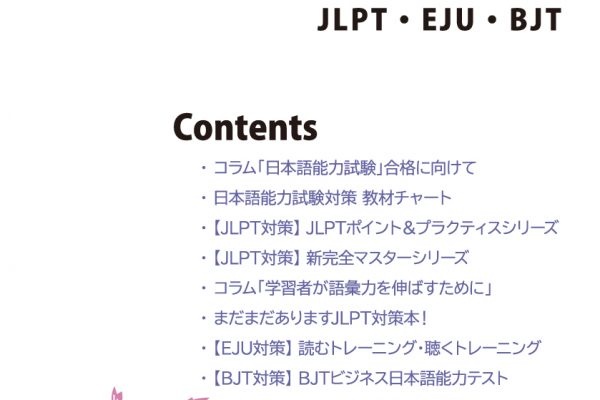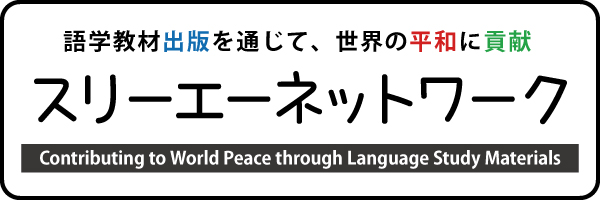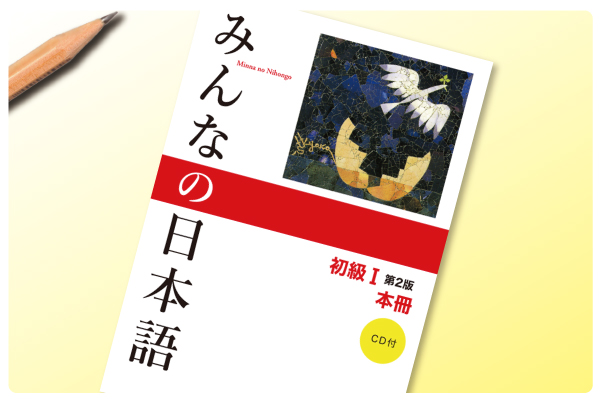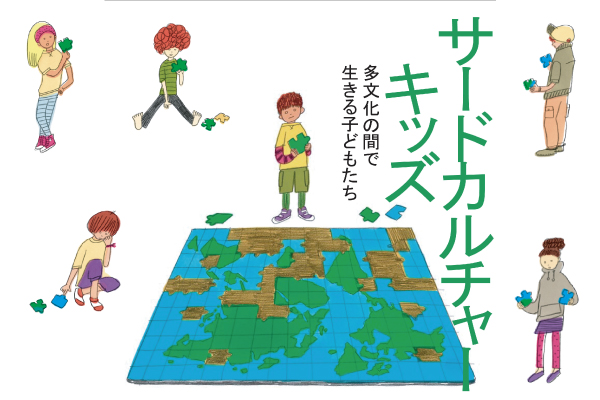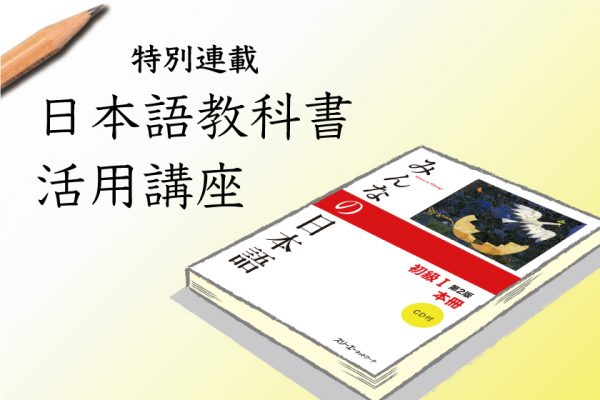セミナーでは「CEFR」「Can-do」「日本語教育の参照枠」について理解を深め、『みんなの日本語 初級』の授業に活かすための考え方をご紹介いただきました。
准教授 西川寛之
*ご所属・お肩書は2025年7月現在のものです
はじめに
2024年、日本語教育機関認定法の施行により日本語教育は大きな転換期を迎えました。また、これ以前から社会的な変化の影響を受け、日本語教育は変化を続けてきました。「留学生30万人計画」の策定、「高度専門職」「特定活動」「特定技能」といった在留資格の新設などがあり、日本社会における外国人の存在が徐々に大きくなりつつあります。これに伴い、外国人の日本語力について一般の人にもわかりやすく説明する共通言語が必要になりました。文法項目(文型など)や語彙数、書ける漢字の数など、知識の量で日本語力を説明しても、一般的な日本社会では通じないからです。外国人の日本語力に関して、社会活動として「何ができるか」に紐づいた説明がなされているのが、共通言語となる「日本語教育の参照枠」です。
教育機関は、そのコースの修了者は「何ができるようになるか」で説明することが求められ、今後はコース説明の際に“Can-do”による記述を用いて到達目標を伝え、入学者と“契約”を交わす形になっていきます。これにより、学習者は到達目標を意識して自律的に学ぶことができ、第三者が教育の質(達成度など)について客観的に見ることができるようになります。
ほとんどの教育機関はこれまでも、言語運用に関して適切な教育成果(学習成果)を出すことが可能なコースを設計し、教育を行ってきたものと思います。現在、私たち日本語教育関係者に求められているのは、専門家ではなく、広く社会一般に向けて、これまで行ってきた教育内容を説明することです。学習者が受ける試験のレベルや、その合否で教育内容や成果を語るのではなく、“Can-do”による記述を使うことが求められています。
適切な教育を行ってきた教育機関には、自信を持って今までの教育内容を“Can-do”による記述文を使って説明していただきたいと思います。もちろん、言語運用の力を伸ばす学習時間をとらずに、試験対策ばかりで、試験以外では何もできないという教育をしていたのであれば教育内容を見直すべきですが……。
今起こっている日本語教育の転換は、これまでに行ってきた教育を否定しているわけではありません。今までの説明方法を変更して、日本語教育を日本社会全体により広く知ってもらえるようにしましょう。
どのような学習者がいるか想定して、コースデザインや授業を考える
1.用語の確認 カリキュラムとシラバス
「コースデザイン」は、学習者が⽬標を達成するために必要な学習内容や活動を体系的に構成することで、その構成要素に「カリキュラム」と「シラバス」があります。
カリキュラムは、「教育課程」全体の大枠を示すもので、教育目標、各科目の教育内容と評価⽅法、各科目に充てる時間の配分などを含み、コース修了時のゴール(目標)に向けてどの科⽬をどのような順序で、どのくらいの時間を使って教えるのか、といった教育全体の計画です。
シラバスは、授業の具体的な計画を示すものです。授業の⽬的、内容、進め⽅、評価⽅法、使⽤教材などが記載され、各授業の詳細な計画書と⾔えます。(「シラバスは、個々の授業科目について学生と教員との共通理解を図る上で極めて重要な存在である。米国では、教員と学生の契約書と理解されている例もある」【参考資料】「教学マネジメント指針」令和2年1月22日(文部科学省 中央教育審議会大学分科会)P.20より)
初級では1つの科目名の授業の中に技能別活動を入れることもあるので、カリキュラムとシラバスを混同しないように気をつけたいところです。カリキュラムにおける教育目標は、コースを通じて学習者に何を身につけさせたいのかという最終的な目標です。Can-doで示すことも可能です。各課の目標や練習はシラバスにあたります。各課の目標もCan-doであるかもしれませんが、これは教育目標のCan-doとは別物です。一つひとつの練習が1つの各課の目標Can-doと一対一の関係である必要はありません。教育目標のCan-doにつながっていることが大切なのです。「教育目標」と「各課の目標」を混同しないよう注意することが必要です。
2.言語教育のシラバスとは
⽂部科学省は、大学のシラバスに授業の概要、授業計画、成績評価の⽅法、教科書・参考⽂献、オフィスアワーなどを含めるよう求めています。文部科学省の「シラバス(様式)」というファイルから項目を抜き出すと、科目名、単位数、担当教員名、履修時期、教員の連携・協力体制、授業の到達目標及びテーマ、授業の概要、授業計画(各回の授業内容)、テキスト、参考書・参考資料等、学生に対する評価を書くよう指示されています。「機能シラバス」や「文型シラバス」というようなことを書くわけではありません。「●●シラバス」という用語は、●●を基準とした学習項目の配列という意味でしかありません。(※これらの「●●シラバス」の捉え方にも注意が必要です。一部の先生方とお話ししていると、「配列された学習項目以外は教えない」という誤解や、場合によっては、「シラバスが教授法を決定するものである」という誤解があると思われる発言を耳にすることもあります。)

認定日本語教育機関における日本語教育では「日本語教育の参照枠」が示すものを参考にコースごとの学習目標を立てることになっています。教育する側は、学習者がそれらの目標を達成できるようにするために、どのようにすれば良いかを考えなければいけません。前述の参考資料「教学マネジメント指針」(文部科学省)のところでもご紹介したように、日本語教育機関は学習者へ、個々の科目における目標と目標達成までの道のりを説明・共有できること(学習者と共通理解を形成できること)が重要になるのです。
3.CEFR、Can-do、⽇本語教育の参照枠がもたらす共通理解
言語教育のコース設計においては、教育目標とその成果に対する社会的な共通理解が必要です。そのために教育⽬標を定め、そこにたどり着くための道のりを逆算する「バックワードデザイン」という視点が重要になります。共通理解は、学習者や学習者と関わる周囲の方(例:留学生を採用したい会社の人事担当者や、アルバイト先の人たちなど)と教育関係者の間の理解です。学習者が勉強した結果、何ができるようになったのかを明確に示すのには、試験のレベルよりもCan-do statementsのほうがわかりやすく、学習者が自身の言語能力を自己評価し、第三者にも伝えやすくなります。また、日本語教育の専門家でなくても学習者の様子を見て、言語学習の成果を理解・共有できるようになります。これが「日本語教育の参照枠」の存在意義です。
4.日本語教育のバックワードデザイン
「バックワードデザイン」と聞くと新しい概念のように感じる方もいるかもしれませんが、目標から逆算して教育内容を考えるというのは、教育にとってはごく当たり前のことで、これまでも行われてきたはずのことです。日本語教育のために言語調査が必要だと言われるのは、「学習者が話したいこと」「身につけたい言語能力」を調査し、そこを学習到達地点(学習目標)として定め、そこにたどり着くために必要なもの(学習内容・学習項目)を教育の場で提供するためです。
「日本語教育の参照枠」を共通の指標とすることで、学習者・教育機関・進学先や就職先の間で言語能力の到達度が互いに理解されます。これをベースに、採用側の求める能力についてバックワードデザインで補う教育が今、求められています。
温故知新、バックワードデザインが今再び注目されているのは、学習到達目標を意識した教育活動と到達レベルの共通理解が、非常に重要視されているという現在の情勢の裏返しだと言えます。
5.CEFRのCan-doと汎⾔語的な考え方・個別言語的な特徴をおさえた教育的アプローチ
「日本語教育の参照枠」が参考にしたCEFRは汎⾔語的な視点に基づいており、Can-do記述(「〜できる」という形)を⽤いることで、⾔語能⼒を記述可能にします。この汎言語とは何でしょうか。例えば、日本語とフランス語のように語族が違うと語順などの言葉の規則も違います。屈折語に属するフランス語などの活用がある言語は、活用が正確にできることが非常に大切です。中国語のように孤立語で活用がなく、語順が大切な言語もあります。膠着語である日本語のように助詞が大切な言語もあります。例えば言語能力の評価指標で「正確に活用ができる」という基準を設けても、中国語(孤立語)には活用がないので、「活用ができる」という文法的な基準は中国語力の評価指標には使えません。1つでもその評価指標が使えない言語があると、それは共通の指標にはできません。そこでどんな言語でも共通に説明できる基準を作るために「汎言語」という概念が活用されることになりました。汎言語という概念は各言語の文法的・語彙的・音韻的な特徴を削ぎ落としたもので、現時点では言語能力の説明にCan-doが用いられています。
汎言語と対になるものとして「個別言語」があります。個別言語は、一つひとつの言語の文法的・語彙的・音韻的な特徴を含めたもので、先ほどの「活用」や、「漢字」などは個別言語的な特徴のひとつということになります。言語教育においては、個別言語的な特徴をおさえた学習も大切だということを忘れてはいけません。
CEFRの言語能力記述文におけるレベル表示は言語ごとの特徴を排除し、汎言語的な視点で言語能力を評価することが特徴です。教育方法のアプローチではなく、教育の結果の示し方として、学習者は何ができるかということを基準にCan-doの形で記述されます。このデメリットとして指摘されるのは、まず、各言語の文化的なこと、文法的、語彙的、音韻的特徴の重要性が軽視されるおそれがあることです。さらに、個別言語としての文法や語彙を含む学習過程の評価について、何をどのくらい理解し身につけたかを示すのが難しいことです。一方、メリットは言葉の評価に関して言語を超えて、「この人はこんなことができる」という説明ができることです。レベルの共通認識を活かしてコース設計が行われれば、国や学校などを移ったとしても、移動先でそれまでに勉強してきたことの続きの学習がしやすくなります。
汎言語的な視点と個別言語的な視点の重要性をおさえて、Can-doを活用し、文法や文化のようなもの、汎言語では言い表せない個別言語の特徴も考慮して、授業を組み立ていく必要があります。
6.言語教育:知識と技術 汎言語的な視点と個別言語的な視点からバランスをとった教育
「汎言語的な視点と個別言語的な視点からバランスをとった教育」について考える資料として2つ取り上げます。ひとつはアーミーメソッド、もうひとつはACTFL-OPIです。いずれも、学習方法、評価方法で知られているものです。なぜ取り上げたかというと、それぞれが一定の成果をおさめたからです。その成果はCan-doと異なるものではなく、またCan-doを日本語教育に利用したのはCEFRよりACTFL-OPIが先でした。そこで、この2つを取り上げて「バランス」を考えたいと思います。
アーミーメソッドの⼯夫が⽰すもの
温故知新でアーミーメソッドについて思い出してみましょう。アメリカで行われたアーミーメソッドは、教育内容を2つに分けていました。ひとつはシニア・インストラクターが文法や文化などの知識を英語で教えること、もうひとつはドリルマスター(学習言語の母語話者)が自然な音声を聞かせ、徹底的に口頭での反復練習・運用練習を課すことです。日本語指導の際には、ドリルマスターとして日本語母語話者が現場に入っていたと言われています。日本の日本語教育機関の先生は、多分この両方の役割を持たなければなりません。
教室では、知識を教えることと運用練習どちらも必要です。この知識については、今現在、色々なものがあります。先生がこの役割をしなくても、翻訳や通訳のツールもあります。国際交流基金が作成した「JFスタンダードの木」の図を参考にすると、知識(例:文法規則、語彙の意味)は、「根っこ」に相当し、「枝葉」は運⽤能⼒となります。土の中と地上の部分の両方を教室内で育てていくことがポイントです。具体的にはアーミーメソッドの音声重視、それから反復練習に加えて場面設定を考えて練習すればCan-doと結びついていきます。それをひとつのゴールにできます。つまり、反復練習も場面練習も両方行うということが大切です。

ACTFL-OPIから⾒た⾔語運⽤の⼒
言語運用の力についてACTFL-OPI(以下、OPI)におけるCan-doを見てみます。OPI(Oral Proficiency Interview:⼝頭能⼒⾯接)は、アメリカ発祥のもので、言語運⽤能⼒を評価するための⾯接形式のテストです。OPIでは「運用できる力=ゴール」と捉えます。知識の量ではなく、実際に言語を使って何ができるのかという運⽤能⼒を重視します。ただし、そのゴールに到達するためには、運用できなかったら話にはならないのですが、知識も大切にしています。
OPIの評価基準は4つで、(1)タスク遂⾏能⼒、(2)社会的場⾯/話題領域、(3)談話の型、(4)正確さです。OPIでは(1)の「タスク遂行能力」をテストによって評価します。そのゴールに到達するために必要なものとして、(2)の「社会的場面/話題領域」つまり、色々な社会的場面に対応できる知識や文化的知識、それから色々な話題に精通していたり、知っていたりすることが必要となります。また、(3)の「談話の型」は言語によって違うと言われていますので、それぞれの言語の場面に合わせた談話の型を提供することが教師の仕事で、学習者はそれを選ぶ力を身につける必要があります。そして、(4)の「正確さ」は文法・語彙・発音・社会言語学的能力(個別の社会における言葉の選び方、態度)・語用論的能力(言葉を文字通りに理解するだけでなく、話し手の意図や状況を理解する力や、皮肉や冗談などを理解し使う⼒)・流暢さの6つに分かれており、それぞれ必要なものを学びます。
OPIでは、(1)の「タスク遂行能力」はテストによって評価し判断しますが、(2)から(4)まで、そして(4)の中の下位区分の6つ、それぞれについては教育で伸ばしていくことを提唱しています。「Can-doの授業」という表現に惑わされて、上記の(2)(3)(4)をおろそかにするのは本末転倒で、語彙や文法、文化や常識といわれることも、発⾳や文字の正確さも、すべてCan-doに向けた授業を実践するためにシラバス化する必要があります。
つまり、様々な知識、談話の型、文法・語彙・発⾳・社会言語学的能力・語用論的能力・流暢さを⾝につけさせるのが「教育」の役割で、それをいつ・どう教育するのかを明示するのがシラバス、どの科目でやるのかを説明するのがカリキュラムです。3か月後、6か月後、1年後、といった節目までに何文字覚え、何ができるのか、どのような文字を学習するのかも、説明する必要があります。語彙も文法も同様に示す必要があります。そして、これらの成果として、3か月後には何ができるか、1年後には何ができるか、これを積み上げて、修了時(卒業時)に達成される目標は何かを示します。
『みんなの日本語 初級』と対照する
文法・語彙・発音・社会言語学的能力・語用論的能力・流暢さを『みんなの日本語 初級 翻訳・文法解説 英語版』と対照してみます。「文法」はⅣ. Grammar Notesに、「語彙」はI. VocabularyとⅢ. Useful Words and Information、「発音」はCDとかDVDなどが利用できます。そして「社会言語学的能力」は「Example Sentences」にあたります。「Example Sentences」は『みんなの日本語 初級 本冊』の「例文」に相当する部分で、訳が付いているのがポイントです。「語用論的能力」も「Example Sentences」と「Conversation」(『本冊』の「会話」)にあたり、どんな会話がなされているのか、そこにはどんな背景があるのか、本には書かれていないようなことは先生が紹介してあげると良いと思います。「流暢さ」については上記を総合したものですので、先生が教室で鍛えてあげる必要があります。

7.教育内容:ゴールまでの道のり・課程・プロセス
コースの設計では何を使って、どこに向かって、どのように指導していくのか、コース修了時に運用できる力のゴールを考えます。そこで、達成する目標からの逆算「バックワードデザイン」を利用します。バックワードデザインは、「日本語教育の参照枠」でも大切なキーワードです。「学習者の進学先がどんなところか、そこではどんな言葉が使われているのか、その学校に行ってみて、その学校の先生たちと話したり、進学先の教科書などを調べてみたりして、そこに向かって必要なことを紹介する」「面接の練習ではどんなことを質問されるのだろうかと並べてみて、そこを目標に勉強する」これもバックワードデザインです。余裕があればもう少し先、例えば進学先が大学であれば、卒業論文が書けるようなレベルまで育てたいと思った場合に、そのことを念頭に置いて教育していく、まずはそのプランを立てることが重要になります。
8.学習内容のリスト化/個別⾔語の重要性
学習内容は段階的にリスト化して整理し、各文型や語彙を具体的な場面でどのように使用できるか、学習者中心の授業を考える必要があります。学習内容のリスト化はとても大切なことです。
学習者が卒業後どうしたいか(目標)は、それぞれ違います。そして何を勉強してきたかも違います。学習者中心の授業をする場合に、その人が求めているものを具体的な場面で、バックワードデザインで作ろうと思った時、教科書だけでは実現できないでしょう。
先述の『翻訳・文法解説』で確認しましたが、教科書には「社会的場面/話題領域」から「正確さ」の文法・語彙・発音・社会言語学的能力・語用論的能力・流暢さまでが並んでいました。これらがカバーできる教材を使い、学習者が求める力を養うアレンジは先生がしていくということが望ましいでしょう。
ゴールまでの道のりには、個別言語の特徴・文化的背景などをしっかりと教えなければいけません。このようなことが汎言語的な捉え方だけでは抜け落ちてしまいますので、個別言語の視点から、しっかりと学習内容を絞り込んで、細かく見ていく必要があるということを忘れないでください。
【参考資料】
・「教学マネジメント指針」令和2年1月22日(文部科学省 中央教育審議会大学分科会)
・「シラバス(様式)」(文部科学省)
・「日本語教育の参照枠 報告」令和3年10月12日(文化庁 文化審議会国語分科会)
・JFスタンダードとは(国際交流基金)
明海大学外国語学部准教授。博士(応用言語学)。日本語教育における文法、評価や指導法を専門とし、日本語の文末詞の研究やOPIをはじめとする会話能力テスト、その他複数のテスト開発に携わる。医療場面における日越コミュニケーションの比較研究や、AI 対話システム・生成AI を活用した日本語教育にも取り組む。